前回の記事で、接着箇所の表面処理と、パテの混合までをお伝えしました。
今回の記事は、実際にパテを塗って穴を塞ぎにかかります。
パテ塗り実施


このように大穴が空いたフランジ部分に、しっかり混合比を合わせて作った高機能パテ GM-8300を塗りこんでいきます。
塗りこみの概念は、パテ⇒アルミホイル⇒パテのサンドイッチ構造です。
※詳細は、前回の記事をご参照下さい。
最初100円均一で購入したバターナイフを使用して塗り込もうとしたのですが、とてもじゃないですがやりにくい。
そこでホームセンターで買ったラテックス製の薄手のゴム手袋を使って塗布。
しかしこれもべたついてしまって、どうにもこうにも成りません。仕方なく素手で塗りこんでいきました。
というわけで、塗りこんでいる最中の写真は少なめです。

一番下にパテを塗りこんだ後、アルミホイルをぐるりと貼り付けました。4枚重ねなのでそこそこ強度はあるはず。破れたりしないように最深の注意をはらいます。
その後、上から塗りこんで終了です。
全体的に塗りました。内側からも塗りこんでいます。
裏面などの写真は別途お見せします。
乾燥工程(最重要)
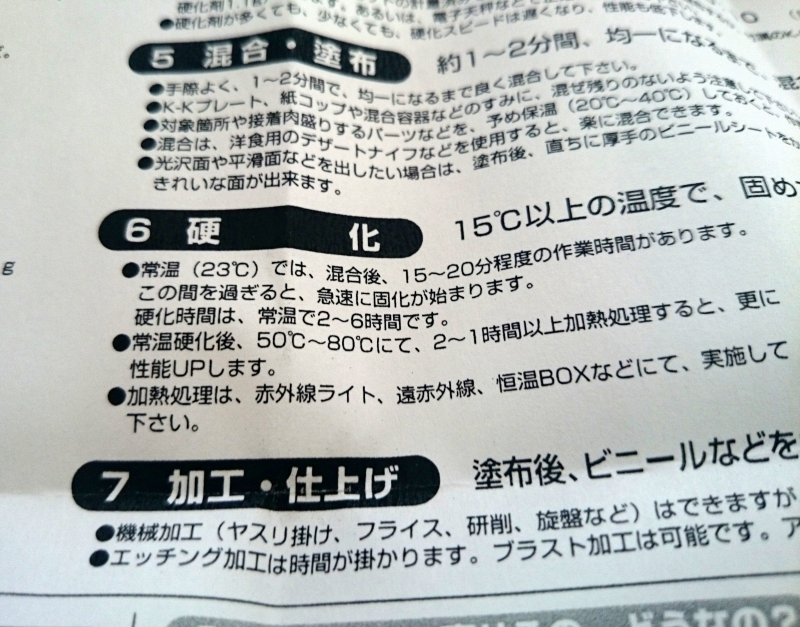
しっかり固めるには、ある程度高い温度が必要です。
作業時は11月で、気温はせいぜい10℃まで上がればいいほう、と言った環境でした。夜になれば0℃近くまで下がってしまいますので、乾燥には非常に不利。
また、
「常温硬化後、50~80℃にて、2~1時間ほど加熱すると、更に性能がUPします」
との文言も有ります。
この手の指示にはしっかり従ったほうが無難です。
とはいえ、加温するためにはそれなりの装置が必要です。
当初考えていたのは、このような赤外線ライトでした。
おそらく1回使ったら、ほぼほぼ使うことはないと思いますし、このライトにはあんまり投資したく有りませんでした。何かこう、今持っているものを流用できないかなぁと思って探してみたら、
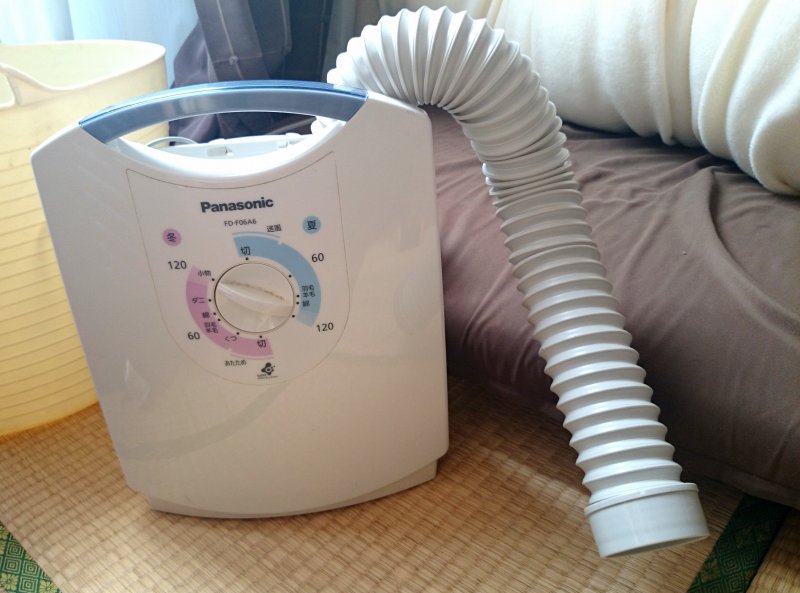
これです。布団乾燥機。
説明書を見たら、50℃~60℃くらいまでは温度が上がるとのこと。しっかりと加温できれば、乾燥用途には問題ない性能を発揮できるのではないでしょうか?と思ったわけです。
実際にどのくらいの温度になるか測ってみました。
布団の温度を計測します。普通の温度は25℃ですが、
乾燥機を作動させ、温風が出る部分の直近だと51.9℃まで温度が上がっています。
やはり上手く保温できれば使えそうです。
ちなみに使った温度計は、こういったレーザーポインタ付きの非接触式赤外線温度計です。
安物なので、どのくらいの精度で計測できるかは全然わかりません。ただ、沸騰するお湯を計測したら100℃と表示されたことを考えると、大体の温度は計測出来ているのかな~と思います。10℃も20℃もズレることはないかと。±3~5℃位のズレであれば全然許容範囲です。

延長コードを使って、部屋から電源を確保して、乾燥機をラシーンの下に潜り込ませます。

最初のトライは、このようにダクトを回りこませて、温風を当ててみました。
ただこれでは全然温まりませんでした。表面温度すら上がらない。温風で物を温めるには、ある程度閉鎖した空間を作る必要があるみたいです。
温風箱というものがあるのですが、これはダンボール等を使って温風を滞留させて、温度を維持する装置。こういったものを作らないとダメだと考えました。


丁度良い所に、Amazonから送られてきたメール便の袋がダンボール素材であったため、それに中間パイプと温風ダクトを入れました。
その辺にあった紐で口を絞ります。ダンボールは断熱性が高い材料であるため、原理上は、これで簡易温風室になるはずです。


露出している中間接合部の部分にレーザーを当ててみると、36.5℃を示しました。実際に触ってみると、人肌以上に温まっていて、ダンボール袋に近い方を触ると、3秒も触っていられないほどの高温になっていました。確実に50℃以上になっているでしょう。
このまま3時間放置しました。じっくり乾燥します。
乾燥後

3時間の乾燥後、ばっちり固まっていました。

背面もしっかり固まっています。
一段盛り上がっている部分がアルミホイルを巻いている部分です。
フランジのねじ穴の部分にパテがつかないよう、クラランスをしっかり確保できるように気をつけました。


側面から見た感じ。


若干撮影した位置がずれていますが、穴が開いていた部分もこのようにふさがっています。
全面的に、このようにパテでコーティングしました。
塗っていて、この内部を塞ぐのが一番楽しかったです。穴を埋めるのってなにか楽しいw
次のマフラーの準備
フランジの穴ふさぎが終わりましたので、
新しいマフラーを購入し、取り付けの準備します。

次回の記事は、マフラーの取り付けです。
セルフ納車整備・マフラー修理(新マフラーの取り付け) につづく。


















コメントを残す